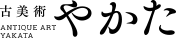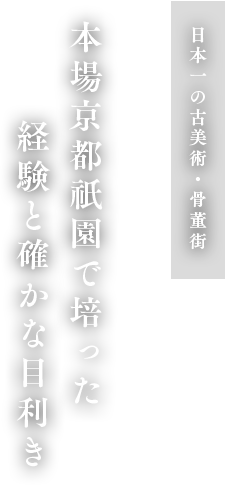高島野十郎の詳しい説明と 買取
明治23(1890)年、福岡県久留米市の酒造家の生まれ、本名彌壽、字は光雄。
父は南画をたしなみ、叔父の大倉正愛は東京美術学校西洋画科を出た洋画家。
さらに長兄の詩人・高島宇朗は青木繁との交流があり、幼少時から絵に対する関心が培われる環境にあった。
美術学校への進学を志したが、父の許可が得られず、明治45年東京帝国大学農学部水産学科に入学。
大正5年、東京帝国大学農学部水産学科を首席で卒業し、研究者としての前途を嘱望されたが、周囲の期待に反して、念願であった画家への道を選ぶ。
独学で絵を学び、美術団体にも所属せず、家庭を持つことさえ望まず、流行や時代の趨勢におもねることなく、自らの理想とする絵画をひたすら追求する超俗的な生活を送った。
「世の画壇と全く無縁になることが小生の研究と精進です」と語っている。
絵は師や画塾に学ぶことなく、すべて独学で、初期から一貫して細密な写実を手掛けた。
坂本繁二郎ら久留米出身の画家たちとは交流があった。
1928年(昭和3年)間部時雄や五味清吉らと「黒牛会」を結成、特定の芸術的主張を掲げたのではなく、互いの研鑽を計る少人数の集いにすぎなかったが、野十郎にとっては生涯唯一のグループ活動となった。
1929年(昭和4年)頃、39歳の時に美術研究のために渡欧し、数年間欧州に遊んだ。
アメリカを経由してパリに滞在、ドイツやオランダ、イタリアへも足を伸ばした。
現地でも誰かに師事することなく、欧州に滞在していた日本人画家と交流することもなく、ひとり美術館や教会を見て周り、現地での制作に勤しんだ。
ミレー、ダ・ヴィンチ、デューラーなどを観た僅かな消息がみられる。
またドイツ・フランス・イタリアなどで、主にルネッサンス時代の絵画に傾倒していた形跡がある。
1933年(昭和8年)に帰国し、その後は故郷の福岡から東京の青山、そして千葉県柏市へと居を変えながら、小さなアトリエと旅先を行き来する生活を続けた。
団体展などには出品せず、個展だけを発表の場とし、あまり他の画家たちと交わることもなかった。
1975年(昭和50年)、85歳で死去した。
「孤高の画家」あるいは「蠟燭の画家」として知られる洋画家で、透徹した精神性でひたすら写実を追求。
野十郎の絵画は、一貫して写実に貫かれているが、単なる再現的描写にとどまらず、その表現や対象の捉え方に独特の個性が光り、それゆえ画面は生き生きとした生命感に満ちあふれている。
卓越した技量に裏付けられた、息詰まるような緊張感さえ感じさせる作品を多く残している。
終生家族を持たず、画壇とも一切関わらず隠者のような孤高の人生を送った。
野十郎は日頃ボロ着でも、町へ出るときは洗練された紳士の服装であったという。
仏心厚く、臨済宗から真言宗に親しみ、空海の「秘密曼陀羅十住心論」を座右の銘とした。
「生まれたときから散々に染め込まれた思想や習慣を洗ひ落とせば落とす程写実は深くなる。
写実の遂及とは何もかも洗ひ落として生まれる前の裸になる事、その事である」と深い精神性を湛えた独特の写実観を示している。
しかしながら、生前にはほとんどその存在が知られることは無かった。
1980年(昭和55年)福岡県立美術館で「近代洋画と福岡展」が開催、同県出身の有名画家に混じり無名の野十郎の作品1点「すいれんの池」が日本ゴム株式会社の出品によって展示された。
当時新人学芸員の西本匡伸はこの絵に強烈な印象を覚え、散逸した作品76点を集めて回り、1986年(昭和61年)秋同館にて「高島野十郎展」を開催、注目を集めた。
その後NHK「日曜美術館」で放映され全国的に知られるようになり、晩年を過ごした柏市(2003年)のほか、三鷹市(2006年)などでも展覧会が開かれ、同年テレビ東京、2008年(平成20年)には再度NHKでも取り上げられて俄然脚光を浴びるに至った。
和太鼓奏者・林英哲は野十郎に深い共感を抱き、2000年に彼をテーマにした組曲「光を蒔く人」を作曲している。
古美術やかたの店内写真
メディアにも多数ご紹介いただいております
クリックしてご覧ください
メディア紹介 MEDIA
- NHK国際放送で世界に紹介されました。英語版【動画】
- NHK国際放送で世界に紹介されました。日本語版【動画】
- BS朝日「京都ぶらり歴史探訪」で紹介され、中村雅俊さんご来店【動画】
- NHK京いちにち「京のええとこ連れてって」取材【動画】
- 『京都新聞』とKBS京都で鴨東まちなか美術館を紹介頂きました。
- 『和楽』7月号 樋口可南子さんがお店へ!!
- 『婦人画報』2012年5月号
- 『樋口可南子の古寺散歩』(5月17日発行)
- NHK「趣味Do楽」とよた真帆さんご来店!【動画】
- NHK『美の壺』(4月24日放送)
- 『和楽』10月号
- 『Hanako 京都案内』
- 『FIGARO japon』12月号
- 『mr partner』2011年2月号
- 2009年11月 『週刊現代』2009年11月28日号
- 『Hanako WEST』4月号
- 『骨董古美術の愉しみ方』(4月16日発行)
- 『近代盆栽』9月号
- 『Hanako WEST』11月号
- 『ORANGE travel』2006年 SUMMER
- 『婦人画報』2004年9月号
- 国際交流サービス協会に2017年6月7日紹介頂きました。
- 『Grazia』6月号
- 『VISIO ビジオ・モノ』5月号
- 『Hanako WEST』4月号
- 『gli』11月号
- オレンジページムック『インテリア』No.23
- 『MORE』12月号
- 『花時間』7月号
- 『東京育ちの京都案内』麻生圭子著 文芸春秋刊
- 『私のアンティーク』