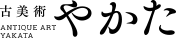永楽善五郎の抹茶道具や煎茶道具の茶道具宅配買取を頂き、諸道具をお譲り頂きました。
写真が5枚あります。くわしくはこちら
 小さな 蓋置 の逸品ですが、永楽善五郎の作品で買取させて頂きました。長年の時代を経てきて 茶の湯 で好んで使われてきた 逸品 で、保存状態 も良く 共箱 も付いており、茶の湯 では日本人好みで喜ばれる 逸品 で買取ました。永楽善五郎は、三千家の職方として務めをはたされ、千家十職 の一員です。最近では 煎茶道具 や中国茶にも抹茶道具にも使われている 茶道具 の蓋置です。
小さな 蓋置 の逸品ですが、永楽善五郎の作品で買取させて頂きました。長年の時代を経てきて 茶の湯 で好んで使われてきた 逸品 で、保存状態 も良く 共箱 も付いており、茶の湯 では日本人好みで喜ばれる 逸品 で買取ました。永楽善五郎は、三千家の職方として務めをはたされ、千家十職 の一員です。最近では 煎茶道具 や中国茶にも抹茶道具にも使われている 茶道具 の蓋置です。
茶道について説明します。
最初は奈良や平安時代に、遣唐使や留学僧によって伝えられ、貴重な飲料でした。その後鎌倉時代頃には、茶の専門書「喫茶養生記」を著し良薬として茶を紹介し、京都栂尾の高山寺に茶を植え広めました。さらに伊勢、伊賀、駿河、武蔵でも栽培され、南北朝時代になると「闘茶」が行われました。安土桃山時代になると、千利休(1522~1591)らによって「茶の湯」が完成し、豪商 や武士たちに浸透していきました。江戸時代では一般庶民にもお茶が浸透して、18世紀後半以降、全国の茶園に広がり、日本茶の主流となっていきました。