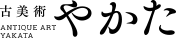煎茶道具や抹茶道具の茶道具宅配買取依頼を頂き、数点お譲り頂きました。
写真25枚あります。くわしくはこちら
 材質は木製で、漆芸作品の 棗 です。輪島塗 の作家、高崎秋峰の作品で、銀地に金の漆で桜と紅葉の雲錦蒔絵が丁寧に描かれており、たいへん美しい平棗で買取させて頂きました。底と内側は金地で丁寧に漆塗りが施されており、日本の昔の 職人技 が冴える素晴らしい 逸品 で買取ました。鮮やかな桜と紅葉の 図柄 で、四季折々に使用できる輪島塗の逸品です。採光の加減で白く光っておりますが、ご覧のように傷んでいる所も無く、保存状態 の良い 茶道具 です。上品な輪島塗の 伝承 された蒔絵の逸品で、綺麗な共箱と共布が付いております。
材質は木製で、漆芸作品の 棗 です。輪島塗 の作家、高崎秋峰の作品で、銀地に金の漆で桜と紅葉の雲錦蒔絵が丁寧に描かれており、たいへん美しい平棗で買取させて頂きました。底と内側は金地で丁寧に漆塗りが施されており、日本の昔の 職人技 が冴える素晴らしい 逸品 で買取ました。鮮やかな桜と紅葉の 図柄 で、四季折々に使用できる輪島塗の逸品です。採光の加減で白く光っておりますが、ご覧のように傷んでいる所も無く、保存状態 の良い 茶道具 です。上品な輪島塗の 伝承 された蒔絵の逸品で、綺麗な共箱と共布が付いております。
煎茶や抹茶の簡単な歴史について説明します。
最初は奈良や平安時代に、遣唐使や留学僧によって伝えられ、貴重な飲料でした。その後鎌倉時代頃には、茶の専門書「喫茶養生記」を著し良薬として茶を紹介し、京都栂尾の高山寺に茶を植え広めました。さらに伊勢、伊賀、駿河、武蔵でも栽培され、南北朝時代になると「闘茶」が行われました。安土桃山時代になると、千利休(1522~1591)らによって「茶の湯」が完成し、豪商や武士たちに浸透していきました。江戸時代では一般庶民にもお茶が浸透して、18世紀後半以降、全国の茶園に広がり、日本茶の主流となっていきました。